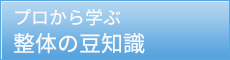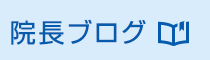▼肩こりへの負担を減らし、根本改善を目指すために必要な考え方
今回の記事では、
「肩こりの原因となる癖の正体」
について解説していきたいと思います。
肩こりの原因を考えるにあたって、
『ヒトの生活様式の歴史と肩こり』
からヒモ解き、なぜ肩こりに悩むヒトが多いのか解説していきたいと思います。
ここで、
ヒトの生活様式の歴史をふりかえってみると、進化の過程で今の当たり前が変わっている事に気づきます。
国立科学博物館の馬場悠男名誉研究員(元人類研究部長)によれば、約600万年前のアフリカにいた人類の祖先、猿人はすでに直立していて、約300万年前には完全な直立二足歩行になったそうです。(日本経済新聞より)
ヒトの歴史の中で最も長い時代は、狩猟採集時代です。
食料を作りだす方法を知らなかった時代には、人々は、けものや魚を捕らえ、木ノ実や貝などを集める生活をしていたとされています。
紀元前2,900年ごろ栄えたとされる、古代シリアの農耕遺跡で発見された骨は変形しており、それが、現在確認できる肩こりの始まりであるとされています。
そして、ヒトが獲物を追っていた狩猟などの生活をやめ、農耕を始めてから、肩こりが急速に増えだしたと考えられています。
これはある一定の動きを繰り返す「重労働による局所への負担の蓄積」によるものです。
それから時代は進み1760年代の産業革命により、ヒトの労働は軽減されていきますが、けれども肩こりは増加していきます。
原因は動く機会が少なくなったことにあります。
その後、自動車が普及するとますます動く機会は少なくなり、利便性が増すことで動かずとも生活が送れるようになっていきます。しかし、肩こりは増えていきます。
これは重労働による蓄積と異なり、「動かさない負担の蓄積」によるものです。
そして現代、パソコンやスマホが急速に普及し、ヒトの生活様式は大きく様変わりを見せています。動く機会がどんどん失われて行っているのです。
厚生労働省による国民生活基礎調査(2015年度)における、「肩こり」有訴者率で男の2位、女の1位を占める症状です。(男の1位、女の2位は共に腰痛)。(厚生労働省ホームページより)
(厚生労働省ホームページより引用)
そしてさらに近年では、テレワーク、在宅ワーク、リモートワーク、デスクワーク、オンラインビジネス、オンラインゲーム、オンラインショッピング、メタバース、SNSなどが流行る事で、さらに活動は激減しています。
コロナ流行後には、社会全体でヒトの動きや行動範囲はさらに減少しているのです。「動かさない負担の蓄積」は増えていきます。
お分かりの通り、この「動かさない負担の蓄積」が現代の肩こりの要因の一つです。
特に肩こりには、関連のある脊柱、骨盤、股関節、上肢を整えることで、首肩の血液循環が改善していくことを多く経験しています。
また、姿勢の崩れに影響している内臓の歪みを整えることで、身体の内側の血流を改善させると共に、身体の内側から姿勢の歪みも改善します。
そして、ストレスの影響を受けてる胸椎、肋骨、鎖骨、胸骨、肩甲骨の硬さや歪みも同時に取り除くことで、根本改善が可能となる方が多くいらっしゃいます。
さらに、肩こりの原因になっている水分、食生活、栄養、負担のかかる動作や姿勢に気づき、少しでも日常的に負担を減らすことで改善し易くなっていきます。
いかがだったでしょうか。
以上が本日の内容になります。
今回は、「肩こりの原因となる癖の正体」をテーマにお話をしてきました。
習慣=癖となっているものがほとんどですので、意識をしないと気づき辛いものです。
先ずは、肩こりの原因となっている癖に気づくことから、改善は始まります。
当院では、肩こりの原因に対して、筋肉や内臓、食生活、メンタルの影響など
様々な要因を、アウター、インナー、メンタルという3つの観点からトータルでみることをベースにしてお伝えしています。
癖となっていることは気づきにくいものです。
ご自身の原因が気になる方は、ぜひご相談ください。
次回は
③「肩こりとストレス」
についてお伝えしていきたいと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました。